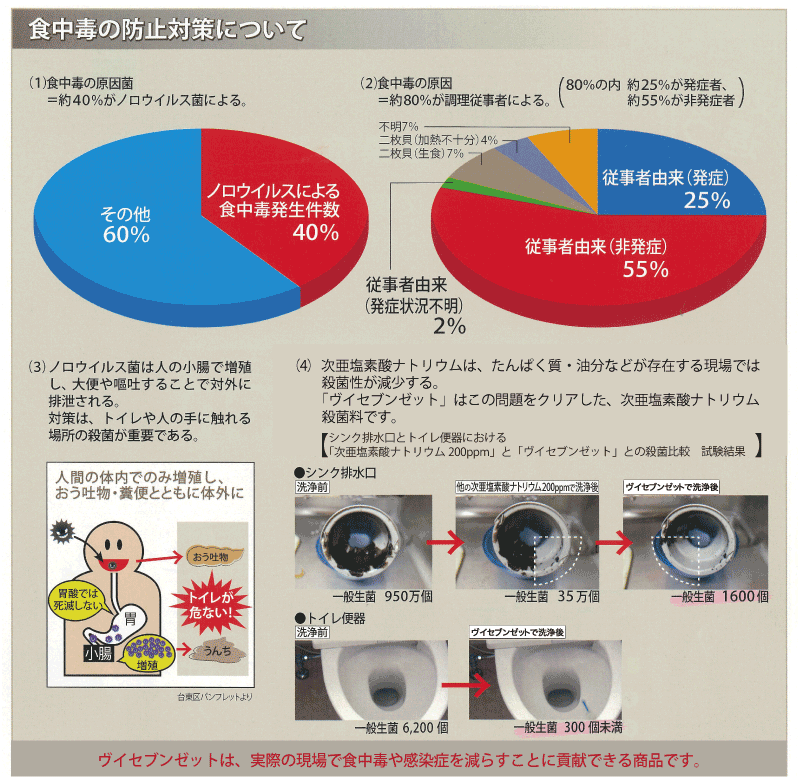食中毒対策
食中毒とは
食中毒は飲食店や施設だけでなく、家庭の食事でも起こり得ます。
普段何気なく行っていることが、予期せぬ食中毒の原因となることがあります。
細菌性食中毒の主な原因菌はサルモネラ菌・大腸菌・カンピロバクターなど、他にもたくさんの種類があります。特徴をよく知って予防対策を行いましょう。
食中毒予防の3原則
◇ つけない
食材の洗浄、調理器具の洗浄
食品や調理用の器具類をしっかり行ないます。食中毒の原因となる病原性の細菌やウイルスなどを洗い落とします。
食品の密封・区分け
食品の密閉・区分けを行ないます。調理前や洗浄前の食品や原材料から調理後の食品に汚染が移らないようにします。
手指の洗浄
手にはさまざまな雑菌が付着している可能性があります。食中毒の原因菌やウイルスを食品につけないようにしましょう。
調理を始める前、生の肉や魚などを取り扱う前後、作業の途中でトイレに行ったり鼻をかんだりした後には、手を洗うことが必要です。
◇ 増やさない
冷蔵:10℃以下、冷凍:-15℃以下、温蔵:65℃以上
細菌の多くは30℃前後の環境で増殖が活発になります。また、65℃以上の高温または10℃以下の低温では増殖が遅くなります。マイナス15℃以下では増殖が停止します。
食中毒の原因となる菌を増やさないためには、冷蔵庫・冷凍庫などの低温、もしくは65℃以上に保たれた温蔵庫で保存することが必要です。
計画的な仕入れ、先入れ先出し
肉や魚などの生鮮食品やお総菜などは、購入後、できるだけ早く冷蔵庫に保管します。
なお、冷蔵庫に入れても、細菌はゆっくりと増殖します。
そのため、冷蔵庫を過信せずなるべく早く使用することが必要です。
◇ やっつける
加熱による殺菌
食中毒の原因となるほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅します。肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安全です。
特に肉料理は中心までよく加熱することが必要です。二枚貝などノロウウイルスよる汚染の恐れが高い食品は、中心部を85~90℃で90秒以上加熱します。
薬剤による殺菌
まな板、包丁やふきんなどの調理器具にも、細菌やウイルスが付着している可能性があります。特に肉や魚、卵などを使った後の調理器具は、洗剤でよく洗ってから、煮沸消毒をします。
さらに、アルコールや塩素系漂白剤などの殺菌剤の使用も効果的です。
プロが選ぶ食中毒対策 ヴイセブン ゼット
食品添加物・殺菌料ヴイセブンゼットはノロウイルスを始め各ウイルス・細菌に対し、即効性に優れた「食品添加物次亜塩素酸ナトリウム」塩素濃度200ppm(500ppm)を主成分とした、除菌・消臭効果と有機物の洗浄効果があります。